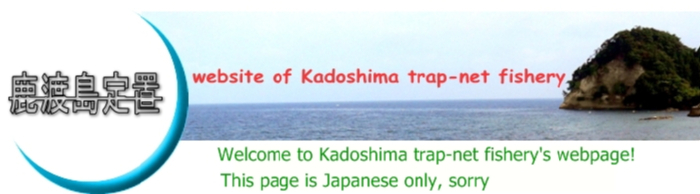魚の活絞めと神経抜き
鹿渡島定置では、神経抜きの技術を取り入れています。
魚介類は死後、次のように段階的に状態が変化していきます。
- 絶命⇒死後硬直開始⇒完全硬直⇒硬直解除⇒腐敗
死ぬと筋肉のエネルギー源であるATP(アデノシン三リン)の供給が絶たれ、
筋繊維が徐々に硬直していきます。そして、時間の経過と共に緩やかに硬直が
解けていきます。この時、ATPが自己消化によって分解されうまみ成分へと変化
します。
死後硬直が完了するまでは、身はまだ活きている状態に近く、鮮度も保たれています。
活絞め及び神経抜きには、主に次のような効果があります。
死後硬直を遅らせて鮮度を保つ
死後硬直が進行するよりも先に延髄及び中枢神経を破壊することで、 ATPの自己消化が大幅に遅れ、 新鮮さが長持ちします。
脱血
血管を切り血を抜くことにより、 生臭さを押さえることができます。また、身の透明感が増します
ご要望に応じて、神経抜きした魚を出荷しています
鹿渡島定置では、神経抜きを日本でもいち早く取り入れた明石浦漁協に
社員を派遣し、神経抜きの技術を習得してきました。
現在、ご希望に応じて、神経抜きした鮮魚を発送しています。
活絞め・神経抜きの手順
(1)活絞めによる血抜き
エラから刃を入れ、血管を切ることで血を抜きます。


(2)延髄を破壊

錐で脳及び延髄を破壊します。これによって、死後硬直を促す信号がストップします。
(3)背骨に沿って中枢神経を破壊

引き続き、先ほど錐で開けた穴から背骨に沿って針金を入れ、中枢神経を破壊します。
こうして、死後硬直の進行をストップさせます。
(4)適温まで冷やす

神経抜きの処理をした後に、冷海水で適温まで冷やします。この時に冷やしすぎると
かえって死後硬直の進行が進んでしまうので、温度管理には十分に注意します。
そして、発砲容器などに詰めて発送します。